- Home
- 小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作
小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作
- 2024/2/10
- 未分類
- 小さな息子2人を抱え私はシングルマザーになった…絵本『こんとあき』を通した親子の絆|絵本の日アワード2023年受賞作 はコメントを受け付けていません
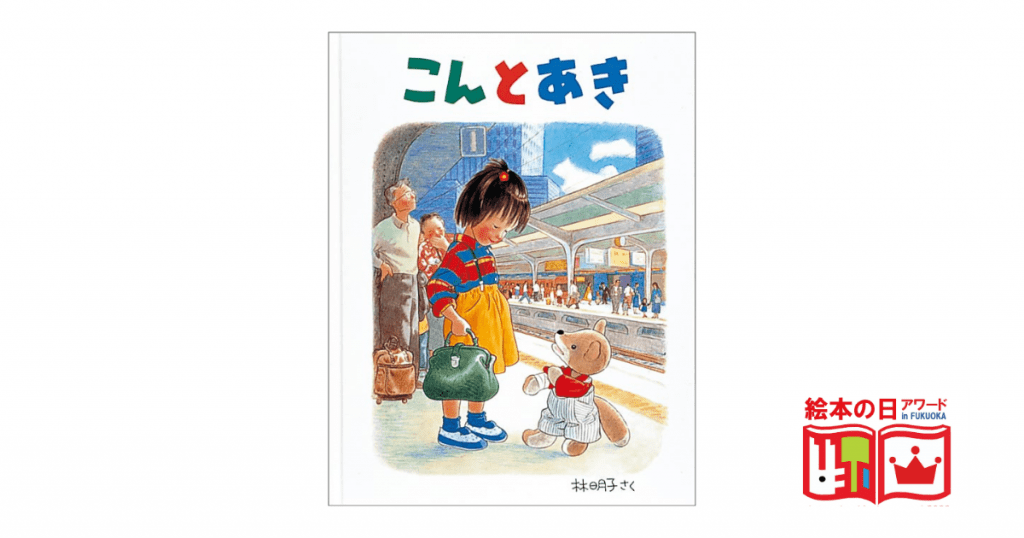
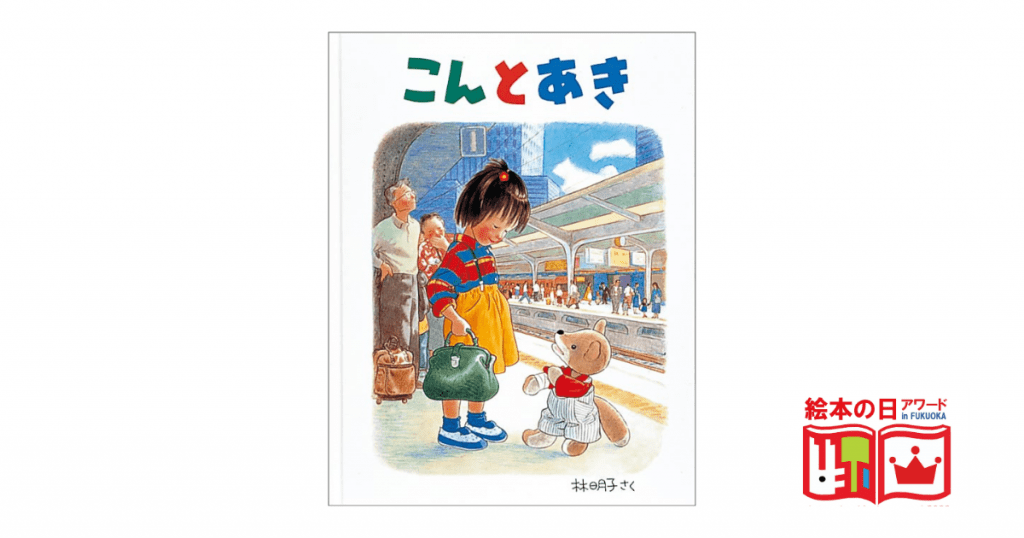
掲載の記事・写真・イラスト等すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます
Copyright © 株式会社エンファム.イベント&メディア All rights reserved.